この記事は2025年1月5日に作成しました。
就労支援員の給与は、決して高い水準と言えないのが現状です。
そのため副業を検討している就労支援員も多くいると筆者は感じています。
そこで今回は副業を今まで行ってこなかった就労支援員の方々に向いている収入の稼ぎ方についてまとめていきたいと思います。
筆者はこれまで物販、アフィリエイト、動画制作、不動産など様々な副業を経験し、現在は副業から法人成りさせています。
副業したいけど、どんなものがいいか見えない就労支援員の方にはぜひこの記事を参考に、自分には何が合ってるか検討してほしいです。
ストック収入とフロー収入


まず、収入には大きく2つのパターンがあります。
それはストック収入とフロー収入といい、聞いたこともある人もいると思いますが、以下にまとめます。
◯ストック収入:資産を保有することで継続的に得ることができる収入
ex) 不動産、株式配当、著作権収入、ブログ、etc…
◯フロー収入:時間や労働を提供することで得られる収入
ex) 給与収入、株式の売却益、フリーランスでの仕事、etc…
ストック収入がいわゆる「資産を持つ」というものですね。
そして普段、会社に所属し給料をもらっているのはフロー収入ということになります。
ストック収入は一度確立してしまえば少ない労力で継続的に収入を得られるので、こちらが本当は理想かと思います。
ただし筆者は「就労支援員」が初めて副業を行うとするなら、フロー収入をオススメしたいと思います。
就労支援員にフロー収入がオススメの理由


そもそもストック収入を確立させるには、膨大な時間と労力をかけることが前提となります。
お金があったら不動産とか株はすぐ買えると思うかもしれませんが、大きなお金を動かす時ほど長く勉強しないと人生詰むかもしれません。
そのため、副業初心者の場合は否応がなくフロー収入から始めるのが妥当です。
さらに筆者が思うフロー収入をオススメする理由を3つ紹介します。
メリット1:短期的に成果が得られる
副業はそもそも収入を増やしたいがために始めると思います。
しかしでは長期的に資産になる可能性のあるストック収入の「ブログ運営」を行ったとしましょう。
ブログ運営を行うにはWordPressの設定やサイトデザインについて、記事の構成や文章について勉強する必要があります。
よく言われるのが、ブログ運営は半年から一年、毎日記事を書いてやっと成果が出ると言われます。
就労支援員としてある程度の収入がすでにある方はじっくり腰を据えて始めるのもいいかもしれませんが、初心者にとっては始めても脱落する可能性が高いです。
そのため、短期的に成果(収入)が得られるフロー収入から始める方が副業へのモチベーションを保ちやすいです。
メリット2:初期費用をかけずに始められるものが多い
前述しましたが、フロー収入は給与収入も含まれます。
つまり所属する会社と別のところで雇用してもらうというのもフロー収入になります。
一部、物販などでは売るための物を仕入れる費用がかかりますが、フロー収入は初期費用がかからないものも多くあります。
副業をするにあたり、気をつけないといけないことは「稼げる情報を買う」ことです。
高額商材は本当にありとあらゆるところで紹介されていますが、99%稼ぐことが難しい物と筆者は思っています。
そもそも副業は収入を得たいために始めるのに、最初にお金を支払うとなるのはナンセンスです。
そのため高額商材など、初期費用が必要なものに手を出すのは絶対に筆者は避けた方がいいと思います。
メリット3:別の場所・業界を経験できる
例えば別の形態の就労支援施設で働いたり、別業界で働くことは本当に良い経験になります。
土日は放課後デイサービスで働く、単純にコンビニでバイトとして働く。
それだけでも自分の所属する職場と違うコミュニティに触れることで、狭くなりがちな自分の世界が広がります。
それに就労支援に関して言えば、転職する際に別の施設からの引き抜きなども多くあります。
より条件の良い職場に転職するというのも収入を上げる可能性があるため、視野に入れて行動したいですね。
【フロー収入がオススメの理由】
◯短期的に成果が得られる
◯初期費用がかからずに始められるものが多い
◯別の場所・業界を経験できる
フロー収入の副業を行う上での注意点
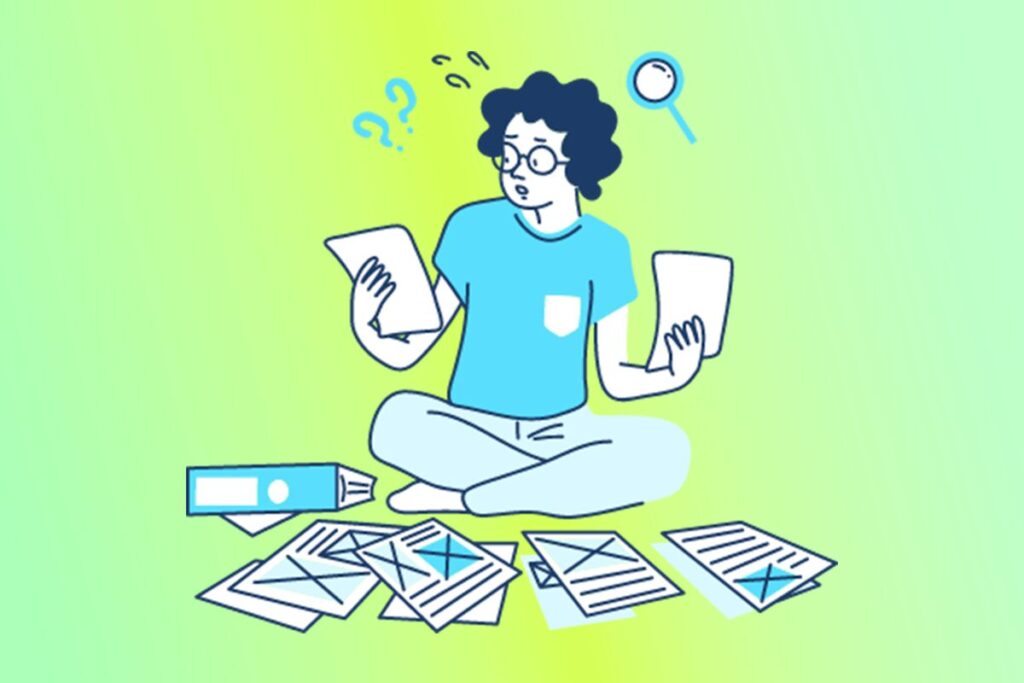
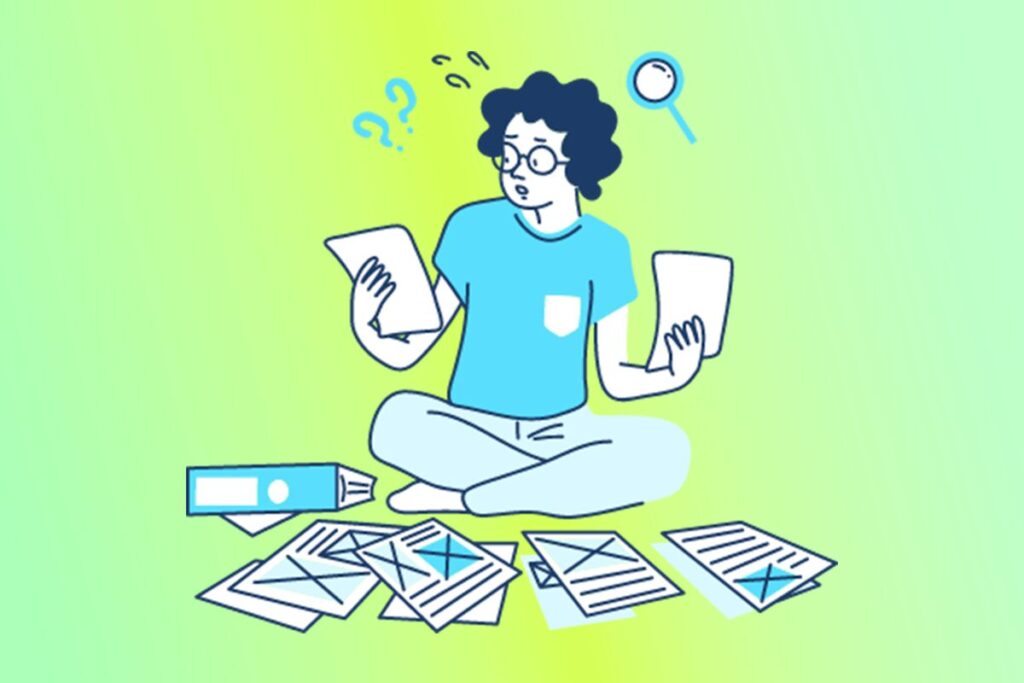
では実際にフロー収入を行う上で、どんなことに注意が必要かを見てみましょう。
もちろん注意する点なんて挙げたら多すぎるのですが、今回は3点にまとめます。
特に副業を行ったことがない方はまず始める前に確認しておきましょう。
就業規則の確認
医療・福祉業界は未だに副業禁止となっている職場が多いです。
筆者の施設に面接に来てくれる人の中にも「副業可能と書いてあるのが魅力的でした」という人もいます。
就業規則は「法律ではない会社の独自ルール」のため、念の為に確認しておくことをオススメします。
しかし小規模な福祉施設の場合、就業規則が存在しない場合があります。
就業規則自体は10未満の従業員数の場合は労働基準監督署への提出義務がありません。
そのため就業規則を作っていないという施設もあるかもしれません。
物販等を行う場合は支出を事前に確認する
給与収入以外で働く場合には、その副業にはどんな支出がかかるかを事前に確認しておきましょう。
例えば、デザイン系であればAdobe社が出しているPremier ProやPhotoshopなどを使う際には月額料金がかかります。
もっと複雑なのは物販で、例えば以下のような支出があります。
◯売れ筋商品を調べるためのツール料金
◯仕入れ値
◯購入した際の配送費
◯メルカリ、ラクマ、ヤフオク等で支払う手数料
◯購入された際の配送資材
◯商品を送るための配送料
パッと思いつくだけでもこれだけ思いつきます。
例えばメルカリで不用品販売を行おうとした際に、不用品だからメルカリ内の最低料金300円で販売し、購入されたとします。
家にあったTシャツをメルカリで販売(仕入れ値0円)
メルカリでは商品の購入代金の10%がかかる
商品をむき出しで送れないため、OPP袋や箱等を購入
発送する商品によって配送料は大きく変動
結局、300円で購入されても、支出は306円となってマイナスです。
これは元々あった不用品販売なのでわかりやすいですが、仕入れた商品を販売するとなるとさらに計算する項目が増えます。
そのため、自分がやりたい副業についてまずはどんなところに支出が発生するかを調べておきたいですね。
給与収入の場合は扶養控除申告書は主たる事業所のみ提出する
一般的に年末調整の時(本来はその年の1回目の給与発生時)に出す扶養控除申告書という書類があります。
その書類は1年に1箇所だけしか提出できず、自分が本業として勤めている会社に提出します。
しかしこれを従たる事業所(バイト先)に提出してしまうと、2重で扶養控除申告書を提出したことになります。
この場合、税務署が2箇所から扶養控除申告書が提出されたと気付き、会社に確認の連絡がいく場合があります。
もしも副業を本業に隠して行っていた場合、この連絡でバレる可能性があります。
就業規則等で副業をしても問題ない職場だったらいいのですが、副業を就業規則で禁止している場合厄介なことになります…。
そして一度出した扶養控除申告書を取り下げて適切に処理するのは面倒な手間がかかります。
このような税金に関する注意点はたくさんありますが、給与収入でまずは副業を始める際には扶養控除申告書の2重提出に注意が必要です。
【フロー収入の副業を行う上での注意点】
◯就業規則を確認
◯物販等を行う場合は支出を事前に確認する
◯給与収入の場合は扶養控除申告書は主たる事業所のみ提出する
まとめ
今回は就労支援員が副業を行う際にストック収入とフロー収入のどちらがオススメかをまとめました。
筆者は副業を始める時には、まずは副業で達成感を感じるためにフロー収入をオススメしていますが、最初からストック収入を目指してもいいと思います。
ただし前述したようにストック収入は時間がかかるし、大きくお金が必要な場合もあります。
就労支援員は全国的な平均給与を見ると、決して高い水準の給与をもらっているわけではないようです。
そのためまずはフロー収入で副業を始めてみて、慣れて時間が取れるようになったらストック収入に向けて勉強したりして並行していけばいいと思います。
副業は会社で給与を稼ぐ以外の、自分の力でお金を稼ぐという経験になります。
まずは副業に割くための時間を1時間でも確保して、ぜひチャレンジしてみてもらえたらと思います。
一歩目を踏み出すのが一番大変ですが…ぜひチャレンジしてみましょう。





