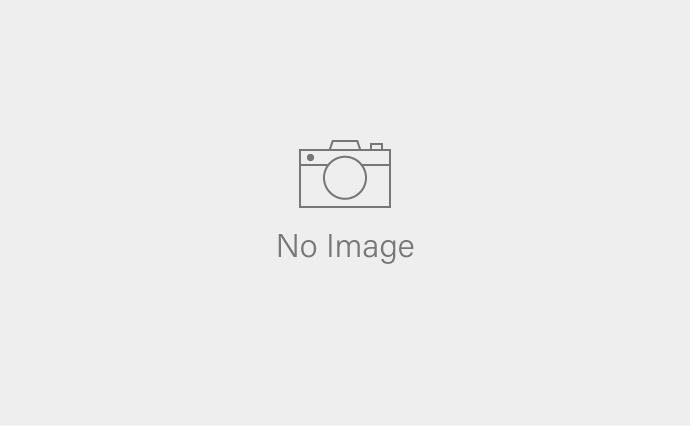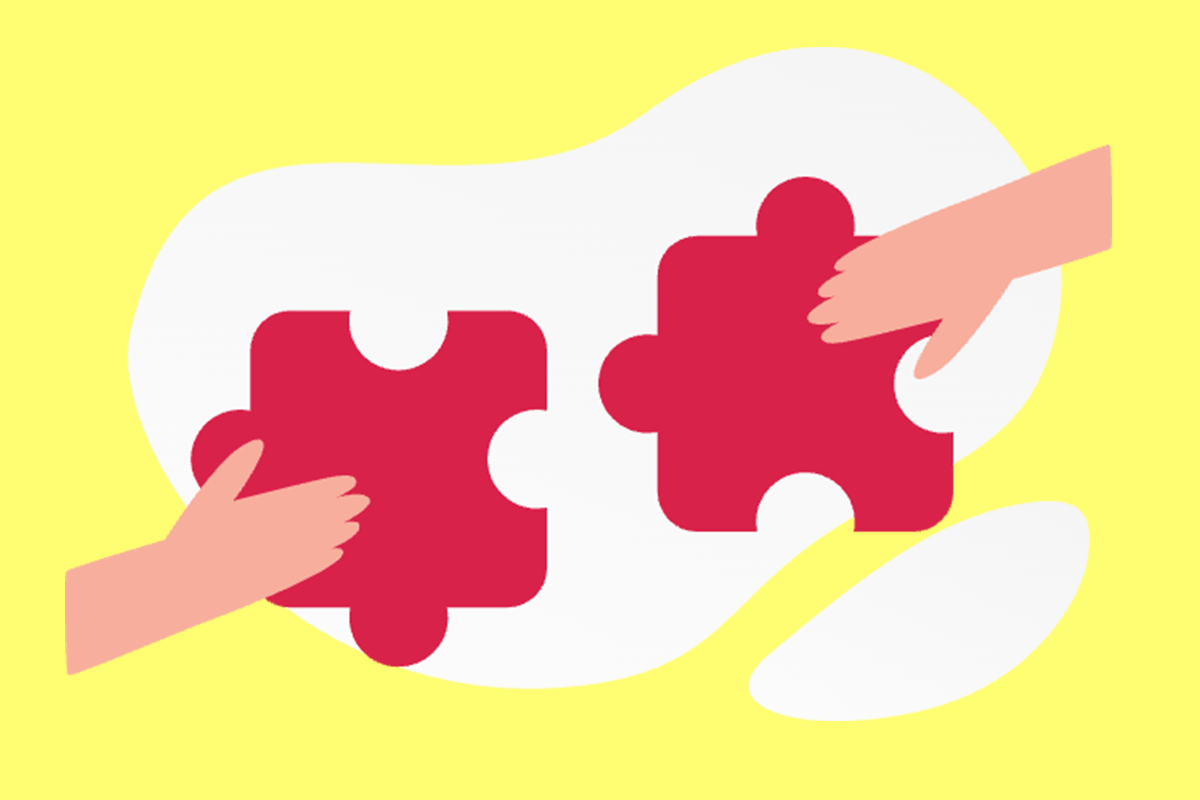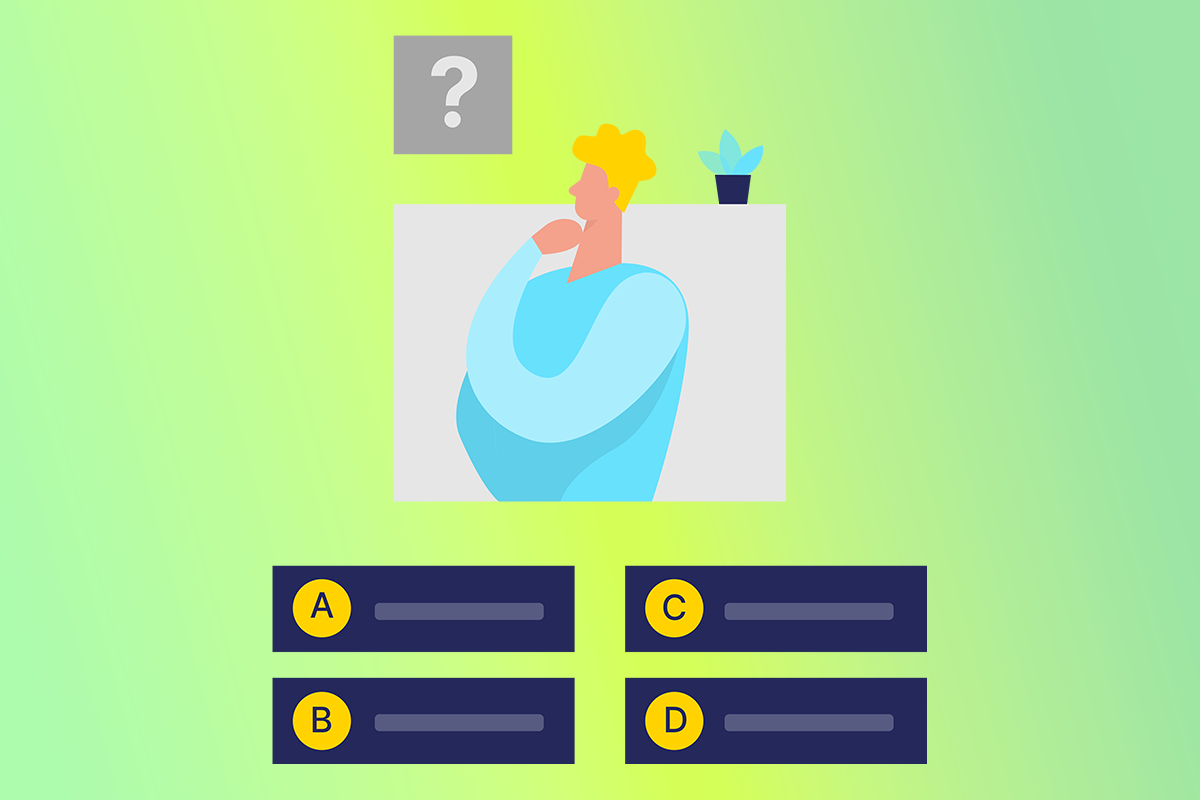この記事は2025年1月13日に作成しました。
誰にとっても、自分のことを客観的に見ることは難しいものです。
特に障害者の方々にとっては、様々な病状が前提にあり、自分の生活を送ることで精一杯なことも多くあると思います。
そのため自分の心や体の変化をすぐに察知することが難しいことも多々あります。
気づかないうちに、どんどん症状が悪化している可能性もあるかもしれません。
この記事では障害者の方が自分では気づきにくい点について、就労支援員だった筆者が就労支援施設における悪化している可能性のあるサイン3つをまとめます。
「もしかしたら自分かも」と思えるものがあったら、一度今の自分の生活について省みて、良い方向に進めるきっかけになったら嬉しいです。
サイン1 身だしなみ(体臭)がキツくなる

就労支援員として現場に立っている中で、体臭がキツイ人は情緒が不安定、もしくは情緒が不安定になる前兆というのはよくありました。
体臭といっても、腋臭などの生理的なものというよりは、入浴していない汗臭い「すえた臭い」ですね。
こういう臭いが強くなる人はしっかりと入浴していない、もしくは服を洗濯できていない人です。
体験した人が多いと思いますが、友達の家などに行った際にその人の家の独特の匂いはあり、本人にその事を伝えても「普通じゃない?」となります。
障害者のその人にとっては自分では気づかない臭いが、周囲の人にとってはキツイ臭いということがあります。
体臭が不調の気づきやすい点ですが、他にも以下のようなことでも不調に気付くことがあります。
【不調になると起きやすい身だしなみのサイン】
◯服装でボタンを掛け違えてて気づかない
◯髪が油ぎってギトギトしている
◯爪が伸びて垢が溜まっている
身だしなみを整えられないということは、他の人から自分がどういう風に見られているかを気にしていないということになります。
自分の生活を送ることに精一杯で、他の人から見た自分を想像するのが難しいのではないでしょうか。
もしも家族等に臭いのことを言われたら、それが一つ不調のバロメーターなのでご注意ください。
サイン2 収入に見合わない買い物をしてしまう
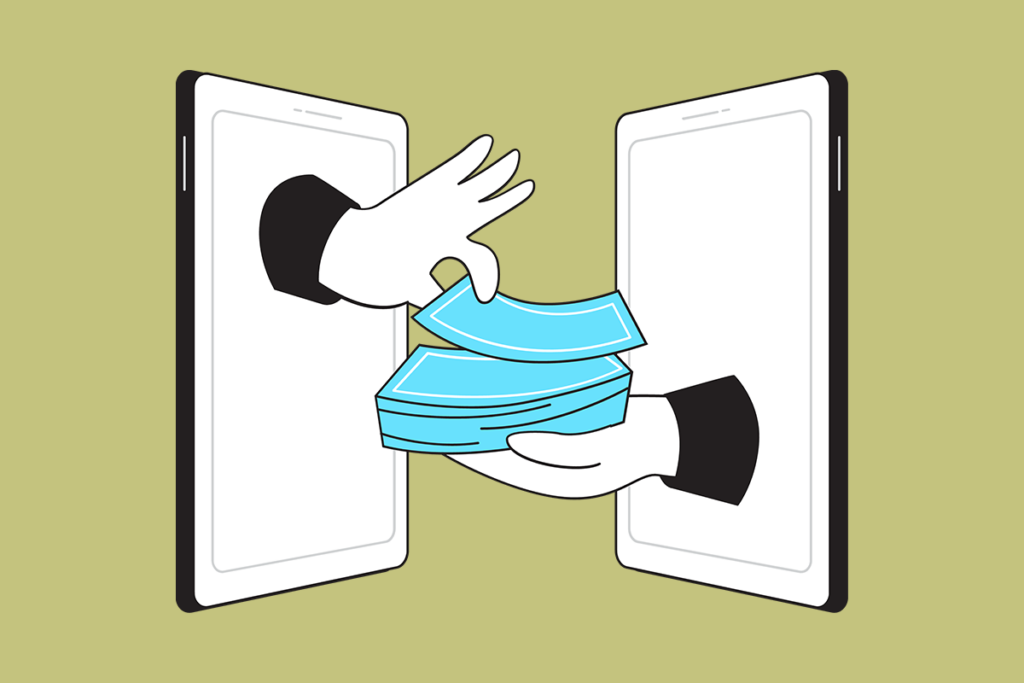
障害者の方でなくても、ストレスが溜まったら買い物して発散するという人はいるかと思います。
買い物はストレス発散になりますが、それでも長期的な効果はなく短期的なストレス発散の方法と言われますね。
障害者の方々にとっても同じですが、特に双極性障害にみられる「躁状態」の人は注意が必要です。
消費者庁が2019年に公表している事例があります。
この中で紹介されている障害者の方が陥ったトラブルの中で、筆者が出会った似たケースが以下になります。
【障害者の方が陥った買い物でのトラブル例】
◯自分の生活に見合わないスマホやWi-Fi契約
◯スマホゲームの過度な課金
◯ネットショップでの過度な買い物
◯健康や収入を上げるためなど将来を言い訳にした高額買い物
これらのケースは本当によくあります。
そもそも、障害者の方々にとって自分の収入がどれほどあるのか(障害年金等)を家族が管理する人も多くいると思います。
そのためぜひ、まずは自分には月にどれだけの収入があるのか、どれだけのお金を使うことができるのかを調べてみてほしいです。
筆者が知っている方で、お金を借りてまで買い物をしてしまい自己破産までしたケースや、車を購入したというケースまでありますので…
ぜひ買い物を「してしまう」という方はご注意ください。
サイン3 怒り周囲の人に発散してしまう

人は誰しも自分の思い通りにならないとストレスを感じて、時には怒ってしまうものです。
ただ基本的に怒りを感じても衝動的にキレ出すようなことはあまりないと思います。
しかし障害があるが故に、怒りを家族や就労支援員に向けて攻撃することもあります。
そして怒りの発散の方法は何も暴力だけでなく、他にも以下のようなものもあります。
【怒りを発散するための周囲への攻撃方法】
◯「俺が△△なのは××のせいだ!」という責任転嫁などの暴言
◯「小遣いを渡さなかったら…わかるよね?」という脅し
◯声をかけても返答をしない無視行動
◯他人の意見を聞かずに一方的に決めつける攻撃的言動
他にもあると思いますが、上記のようなケースは多いと思います。
家族ではなく、あくまで他人である就労支援員に対しても怒りが抑えられないような状態だと症状はかなり良くない可能性もあります。
あくまで筆者の持論ですが、障害者のいるご家庭は家族も障害を負ったということはよくあると思います。
元々は普通に生活していた人が、家族が障害者となったことで自分も障害を負ってしまう。
家族は最大の味方であることが多いですが、同じ人間で心に傷を負うし、ずっと健康でいられるなんてことはありません。
ぜひ自分が怒りやすくなって、家族に怒鳴ったりすることが多くなったと自覚したら本当に注意してください。
まとめ
この記事では障害者の方が生活していて、症状が悪化しているかもしれない3つのサインについてまとめました。
前述していますが、障害者の方は特に自分の体調や心の変化については自覚しにくいことが多いです。
そして周りの人は気づいたとしても、どうすればいいかわからないことが多いと思います。
この記事を読むのが障害者の方だけでなくご家族の方もいるなら、まずはお住まいの地域の役所に行ってみてください。
そこから福祉や医療のサービスに繋いでくれるかもしれません。
障害は基本的に自分や家族だけでどうにかするには限界があります。
それよりも公的なサービスを介して専門家に助言をもらいながら、家族は障害者の方を支えるのが良いと思います。
ぜひこの記事のサインを、今一度当てはまるか考えてみてくださいね。